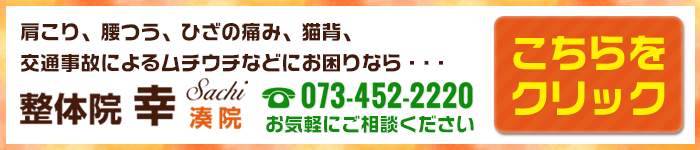膝の痛みと変形は、加齢や酷使が原因!?変形性膝関節症とは!!

年齢を重ねていくと身体には様々な不調が現れてきます。内臓はもちろん、腰や背骨、足、関節など挙げだせばキリがありません。
今回は数ある不調が出やすい箇所の中でも、特に疾患が起こりやすい「膝」に注目してみようと思います。例えば「階段の上り下りがつらい」「長時間歩けない」「O脚が目立つ」といった症状が現れる変形性膝関節症。
この膝の疾患は、加齢や使い過ぎによって膝関節の軟骨が摩耗していき、炎症、痛み、変形がみられる疾患です。では記事を始めてまいります。
膝の酷使や加齢に伴う軟骨の消耗
さて、それでは変形性膝関節症の説明を始める前に、まずは膝関節の構造の確認からしていきましょう。膝はスポーツ選手に限らず様々な年代でケガを抱える方が多く、人体のなかで一番、痛めやすい箇所であるとも言われています。
その理由は日ごろから立つ、座る、歩く、といった動作の時に常に使用される箇所であることはもちろん、強い靭帯や関節に守られている構造になってるからだと思います。
一見すると強いのであればケガはしないのでは?と思われるかもしれませんが、それだけ強く作られている組織は酷使されやすい箇所でもありますし、人体において強く、硬いというのは脆いことと同じです。さらにいえばその強い組織が老化に伴い弱体化していけば、もっとケガをしやすくなります。
では本題ですが、膝関節は大腿骨(だいたいこつ:ふとももの骨)と、脛骨(けいこつ:すねの骨)という二本の大きな骨と、膝のお皿といわれる膝蓋骨(しつがいこつ)によって形成されています。
そしてこれらの骨を軟骨組織が繋ぎ合わせていて、軟骨の外側をさらに半月板と呼ばれる組織が覆う構造になっています。今回のテーマである変形性膝関節症はこの軟骨が加齢や酷使によってすり減ってしまう疾患です。
この軟骨がすり減っていくと骨同士が接触し、その摩擦によって患部が炎症して痛みを発したり、患部の可動域が制限されて動かしずらくなるといった特徴があります。
変形性膝関節症の進行過程

この変形性膝関節症は骨折や捻挫(ねんざ)のように外部からの衝撃で組織が壊されるのではなく、徐々に進行していくのが特徴です。それでは時期別にどのように痛みが現れて、患部の変形などが始まるのかを確認していきましょう。
初期
生活に支障はほとんどありませんが、歩くときに膝のぐらつきや違和感を感じることがあると思います。痛みが現れる場合でも一時的にズキッと痛みますが、すぐに和らいでいきます。この状態は膝関節の軟骨が段々減っていき、軟骨に亀裂が入り始めています。
中期
慢性的な痛みが現れだし、膝の曲げ伸ばしといった屈伸運動や、階段の上り下り、正座などをするのが困難になります。この状態は膝関節の軟骨の摩耗によって骨同士の隙間が狭くなり、膝に体液が溜まり始めています。
後期
耐えられないほどの激しい痛みが常に起こります。この状態になるとその痛みから歩行もできなくなり、お年寄りの場合は、この痛みが原因で引きこもりがちになってしまったりします。
この状態では軟骨のすり減りはもちろん、膝関節の変形もみられ、左右の膝の間が離れていきO脚になっていきます。
変形性膝関節症の原因
この疾患の原因となるものは様々ありますが、発症には膝を酷使しすぎたために起こる一次性のものと、他の疾患の後遺症が原因で起こる二次性のものに分類されます。
一次性の場合、年を重ねることによる筋力の低下、半月板や軟骨組織の摩耗、あるいは肥満によって体重が増えたことによって軟骨が摩耗してしまうのが主な原因です。
二次性の場合、膝関節の骨折や、関節リウマチ、半月板損傷、膝靭帯損傷などの後遺症によって起こります。
変形性膝関節症を患う可能性が高い人の特徴

原因の章でも少し触れましたが、老化による軟骨組織の摩耗はもとより、肥満体質、運動不足の人は変形性膝関節症になりやすい傾向にあります。
例えば働き盛りの年齢で変形性膝関節症を患っている方の多くは肥満が原因です。脂肪や筋肉は増やすことが出来ますが、骨格は一度出来上がってしまえば成長することはありません。
つまり、体重が60キロでも100キロでも同じ骨格が支えているわけですから、当然60キロの方が膝関節にかかる負荷は少なくてすみます。さらに言えば、歩くという行為を行っている時、膝には体重の3倍の負荷が掛かっているといわれていますので、やはり肥満になると膝にかかる負荷が大きくなるのです。
また、運動不足も膝関節には良くありません。膝関節の構造は前述の通りですが、骨を覆う筋肉が衰えていくと膝にかかる負荷は多くなります。
膝周りに限らず筋肉は衰えたり、使用しないでいると硬くなる性質を持ち合わせています。そして柔軟性が失われた筋肉では外から受ける衝撃をうまく吸収することが出来ず、地面を踏むたびに膝関節に負荷をかけてしまうことになります。
予防方法
この疾患は加齢や酷使、あるいは別の膝の疾患との併発によって発症するということはすでに前述の通りですが、関節にある軟骨や半月板という組織は一度すり減ってしまうと自力で再生することは出来ません。
ですから予防するには日々の運動を日常に取り入れることが大切です。これからご紹介するトレーニングはどちらも家で簡単に出来るものですから、ぜひ実践してみてください。
まずは太ももにある大腿四頭筋(だいたいよんとうきん)を鍛えるトレーニングです。
椅子に座り、左右どちらかの足を前方向に伸ばし、そこから「もうこれ以上は無理」という所まで上にあげ、その状態を30秒間キープします。反対側の足でも同じことを繰り返し、出来れば5セットほど行います。
始めてこのトレーニングをすると、次の日には筋肉痛の症状が見られると思います。そうなったら無理をせずに2、3日ほど休み、痛みが消えたらまた行いましょう。
次に太ももの内側を鍛えるトレーニング方法です。床に座り枕などの柔らかく軽い物を両ひざで挟みます。この時、出来るだけ強く挟むと効果的です。その状態を30秒ほどキープして一旦離します。このトレーニングも5セットほど繰り返し行いましょう。
このふとももの内側を鍛えるトレーニングは変形性膝関節症を予防できるだけでなく、O脚やX脚といった足の変形にも効果的ですので老若男女問わずおススメです。
まとめ
今回は、変形性膝関節症の進行過程、原因、予防法などについて確認してまいりました。冒頭でも触れましたが私たちの身体は、年齢を重ねるごとに機能が低下していき、様々な疾患が現れやすくなります。
また文中でも触れましたが膝の関節や半月板は一度すり減ると再生は出来ませんから、今回ご紹介したトレーニングを実践し、いつまでも健康な膝を維持できるようにしましょう。
膝関節に限らず、身体の不調は早期発見が出来ると改善できるものが多くあります、もしも身体のどこかに違和感を感じたら、一度専門家に相談してみましょう。