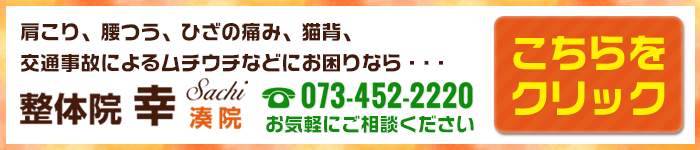スポーツの前後にはストレッチを!シンスプリント!

準備運動の大切さというものはどなたもご存知だと思いますが、部活など日々、行っていることになると慣れて忘れてしまう事もあるかと思います。
もちろん、準備運動を行うのはケガの防止が一番の目的ですし、それによって快適にそして、痛みのないスポーツを堪能できることは素晴らしいことです。今回はそういった準備運動や運動後のクールダウンを忘れてしまう、あるいは成長期のスポーツ選手によく起こるシンスプリントというスポーツ障害について記事を書いていきたいと思います。
シンスプリントは主に膝下のスネや重症化すると足首あたりにまで痛みが広がる疾患なのですが、最近そういった箇所が痛むとお思いの方はぜひ、当記事を読んでみてください。それでは記事を始めてまいります。
シンスプリントとは?

冒頭でも触れていますが、シンスプリントとはスポーツ障害と呼ばれるスポーツに端を発するケガの一つです。その主な原因はオーバーユース(使いすぎ)によるものが多いのですが、成長期の方の場合は成長痛が併発している可能性も考えられます。
またシンスプリントは別名、過労性(脛骨)骨膜炎、過労性脛部痛、脛骨内側症候群など難しい名称でも呼ばれますが、主な原因は骨膜と呼ばれる骨と筋肉との間にある組織に炎症が起きている状態です。
ではシンスプリントとはどのようにして起こっているのか、というお話ですが、スネにはいわゆる弁慶の泣き所ともいわれる脛骨(けいこつ)という骨が存在し、その周りを前脛骨筋(ぜんけいこつきん)、長趾伸筋(ちょうししんきん)という二つの筋肉、そして裏側にはヒラメ筋が存在します。
筋肉というのは使いすぎると硬くなる性質を持っていて、オーバーユースされてしまうと柔軟性をなくしてしまいます。その結果、骨と筋肉がつながっている骨膜に牽引力が働き組織に炎症が起こるというわけです。
ではなぜ同様の症状が成長期のスポーツ選手にも出るかというと、この頃の選手は身体を大きくするために骨の末端にある骨端線(こったんせん)から骨が伸長していき、それに引っ張られるように筋肉や腱などの組織も伸長していくので、結果として常に骨膜が引っ張られている状態にあるのです。
ですからそれに加えてスポーツを行っていると伸長する速度に加えて筋肉が緊張して炎症が起こる可能性が高くなるのです。つまりこれが成長期のスポーツ選手にシンスプリントが起こりやすい理由ということです。
シンスプリントについてもう少し詳しく!

原因を探ることは解決の糸口にもなりますので、もう少し詳しく見てまいりましょう。どのようなスポーツでも同じですが、冒頭にもあるように目的はスポーツを行うことなので、準備運動をしっかりと行うことを忘れてしまう事もあると思います。
しかし、実はもっと重要なのがクールダウンです。クールダウンは運動後にストレッチをして身体の柔軟性を取り戻す作業ですが、私たちが日々多忙を極めていると疲労が蓄積していくように筋肉も疲労をため込む性質があります。
ですから、毎日のように部活や練習を行っていると筋肉が疲労していき、シンスプリントに限らずスポーツ障害を起こしやすくなります。あるいはそういったストレッチだけでない要因もたくさんあるので、以下にはそれがまとめてあるサイトを少し引用してみたいと思います。
シンスプリントの原因は何ですか?予防のため、してはいけないことを教えてください。
シンスプリントは、ダッシュや急ブレーキなどの繰り返す負担により、スネの内側、後ろ側の筋肉やそれを包んでいる筋膜が繰り返し引っ張られることで骨膜にストレスがかかり発症します。これらの負担が骨膜という骨の表面の膜にダメージや炎症を引き起こします。このようなダメージや炎症は、最初のうちは休んでいると治る程度のものですが、オーバーワークで休めないなどにより、完治する間もなく次の新たな損傷が生じ慢性化します。
さらにこれらの負担がかかった骨膜には、炎症に伴い、普段見られないような異常な血管が新しく作られてしまい、その血管と神経が一緒になって増えることで治りにくい痛みを作っていると考えられています。
シンスプリントのリスク因子(この項目が当てはまるとシンスプリントになりやすい)としては
1.扁平足
2.臀部や大腿部の筋力低下
3.柔軟性の低下
4.不適切な身体の使い方、良くない練習
5.下り坂を走ること
6.コンクリートなど硬い路面を走ること
7.不適切な靴の着用
8.体脂肪、BMI(肥満度指数)の上昇
などが挙げられます。
まとめ
今回は成長期のスポーツ選手に多いシンスプリントというスポーツ障害について記事を書いてまいりました。文中にもありますが、準備運動やクールダウンというのは筋肉を休める意味でも大切で、疲労物質を流し、次の日に疲れを残さないことが出来ます。
またその結果、ケガも少なくなり、いつまでも楽しくスポーツが出来るわけですから、ケガの予防に努めて、痛みなく健やかに運動ができるように努力しましょう。