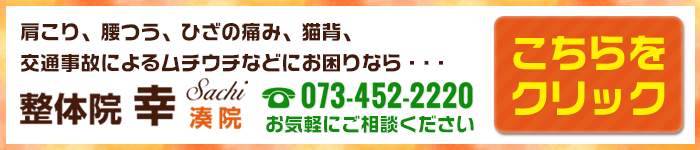心身の疲労の原因とおすすめの疲労回復法

脳は怠け者であるということは昨今、よくメディアでも取り沙汰されますが、私たちの脳は自分のことが一番大切ですから、できるだけ身体を動かさず、ストレスをためず、難しい勉強はせず、が望ましいとはいえ、社会生活を鑑みればそうもいっていられません。
今回は身体や精神を酷使することで、脳が警告を発する「疲労」について記事を書いていきたいと思います。疲労といえば昔は肉体的に衰えを感じだす大人にとっての大敵でという捉え方をしていましたが、習い事や勉強にと忙しくする最近のお子さんにとっても無視できない不調です。
それでは疲労について詳しく確認してまいりましょう。
疲労の原因

一言で「疲労」と言っても激しい運動などで体を酷使した時に起こる肉体的疲労「末梢性疲労」と、勉強疲れなどで脳が長期間緊張状態になることで起こる神経的な疲労「中枢性疲労」の2種類がありますが、いずれの場合もその器質的な原因は同じ、活性酸素による酸化ストレスで自律神経の中枢である脳がダメージを受けることにあります。
末梢性疲労の場合、運動に必要なエネルギーを燃やすために酸素が大量に消費され、その副産物として活性酸素が発生します。通常活性酸素が生産されると体内で抗酸化酵素が働き体内から活性酸素を除去してくれるのですが、この抗酸化酵素の働きを上回る活性酸素が生産されるとこれが神経細胞、特に体温や心拍数を調整している自律神経細胞を攻撃して疲労を引き起こすのです。
一方、中枢性疲労の場合はもっと直接的で、長時間のデスクワークや精神的なストレスの多い状態が長時間続くと、自律神経中の交感神経が過度に優位に働いて脳が緊張状態となり、活性酸素を大量に発生させます。この活性酸素が自律神経細胞を攻撃して、やはり疲労状態になるというわけです。
疲労回復におすすめ方法

そもそも疲労は体が「これ以上心身の活動を続けると体に害が及びますよ」という警告のためホメオスタシス(身体の状態や機能を一定に保とうとする恒常性)の1つですから、その体の勧めに従い活動を休止し体や脳を休める、つまり睡眠をとることが最も効果的な疲労回復法です。睡眠は主に脳を休めるための大切な習慣で、睡眠によって自律神経が整い不要な活性酸素が除去されます。
また末梢性疲労は体のエネルギー不足から来るため栄養のある食事をとることも大切ですが、特に抗酸化作用を持つビタミンCやビタミンEは細胞の代謝を促し活性酸素を除去してくれるため、積極的に取りたい栄養素です。ビタミンCは柑橘系の果物や緑黄色野菜に、ビタミンEはナッツ類やほうれん草、豆乳などに多く含まれています。
また近年強い抗酸化作用を持つ栄養素として「イミダゾールジペプチド」も注目されており、最近の研究調査によってすでに1日200mgのイミダゾールジペプチドを摂ることで疲労を軽減できることが分かっています。イミダゾールジペプチドを多く含むのは鶏の胸肉で、熱によって壊れる成分ではないため蒸す・茹でる・焼くといった調理法で摂取することができますが、長時間の過熱は成分が変質してしまうため比較的短時間での調理が相応しいとされています。
まとめ
今回は思考できる人間であればだれでも感じることがある疲労に着目して記事を書いてまいりました。文中にもありますが、疲労には身体で感じるもの頭で感じるもの、あるいは精神的に疲れる、気疲れするなどように様々な表現が存在します。
例えば仕事や家事の方法を改善したり、ストレスをためない工夫、あるいはストレスを発散する方法をたくさん考えるのもよいですが、下記のような運動を日常に取り入れることで、反対に疲れをためにくい身体づくりができることもありますので、ぜひ、試してみてください。
1日10~30分の軽い運動
運動をすると余計に疲れてしまいそう…と思う方もいるかもしれません。しかし、軽い運動の習慣は、「積極的休養」とも呼ばれており、疲れにくい体づくりのためにスポーツ選手も実践している方法なのです。
ポイントは、負荷の大きい運動をするのではなく、体力に合った、1日10~30分程度の軽い運動をすること。こうした運動であれば、心地良い疲労感の中で血流が改善され、代謝促進による疲労物質の除去も期待できます。また、脳にも栄養が行き届きやすくなり、疲労感の解消効果も。
- 初心者は1日30分程度のウォーキングから
運動不足を感じている方は、ウォーキングから始めてみてください。体力に自信がついてきたら、ジョギングに挑戦してみてもいいでしょう。特に、疲労感で寝付きが悪い方や、眠りが浅いという方は、こうした有酸素運動を取り入れたいところ。
- 下半身の筋トレも◎
脚の筋肉は「第二の心臓」と呼ばれており、全身に血液を届けるための役割を担っています。スクワットやランジ(※)などの下半身トレーニングで、脚を重点的に鍛えていきましょう。
※ランジ…太ももやお尻、ふくらはぎの筋肉を鍛えるためのトレーニング
引用:RENAISSANCE